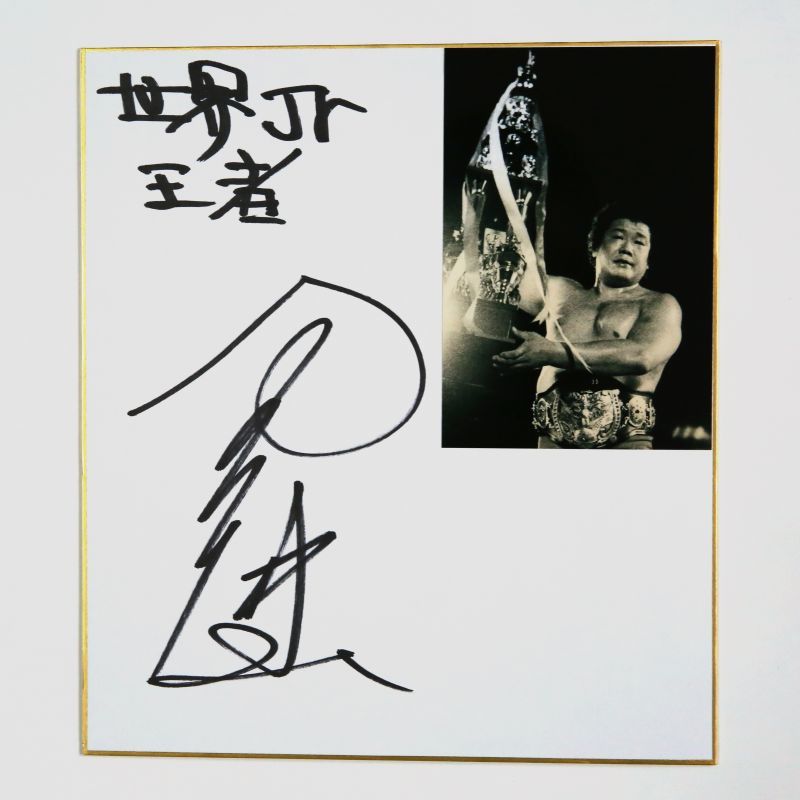井上氏(いのうえし)は、日本の氏族のひとつ。
源姓井上氏
信濃井上氏
『尊卑分脈』によると、清和源氏頼季流とされる。源満仲(多田満仲)の子源頼信が長元元年(1028年)の平忠常の乱を平定して東国に勢力を扶植、さらに三男の頼季が嫡男源満実とともに信濃国高井郡井上を本貫として井上氏の祖となったとしている。
源平の戦いとして知られる治承・寿永の乱では同族とされる村山七郎義直が、村上氏の支族とされる栗田氏と共に市原合戦で笠原氏を相手に戦ったのをはじめ、北信濃の源氏方として平家方と戦いを繰り広げ、平家物語では保科党を率いる井上光盛が横田河原の戦いで源義仲方として参陣して活躍し、信濃源氏の代表格として扱われている。その後は源頼朝に従った様だが、甲斐源氏一条忠頼と共に頼朝から危険視された光盛は、元暦元年(1184年)7月10日に京都から鎌倉に召喚される途上の駿河国蒲原駅で吉川氏や船越氏ら駿河の御家人によって誅殺される(『吾妻鏡』)。承久の乱では光盛の次男井上光清(正光)が仁科盛遠に従い後鳥羽上皇側に立って参戦している。
光盛の誅殺以後、井上氏は近隣の村上氏(清和源氏頼清流)や、同族とされる高梨氏に比して、総領家を中核とする武士団の形成が大きく遅れたとされる。その一方で井上一族では西念のように、親鸞に帰依するなどして仏門に入る者が多く、武士団としての発展が阻害された要因とする向きもある。井上氏は戸隠山勧修院顕光寺に別当職を得るが、29世澄海は大衆(だいしゅ)と合戦に及び、更に文永5年(1268年)には井上盛長が善光寺を焼き払い誅殺された記録が『尊卑分脈』所載の井上系図にある。
文永2年(1265年)には井上正頼が在庁官人として信濃大掾を称している(『鎌倉遺文』)。建治元年(1275年)5月六条八幡新宮の造営費用が全国の御家人に求められると、信濃国に住む井上太郎跡(後裔)が3貫文を納めている。
南北朝時代の井上氏に関しては史料が残されていないが、観応の擾乱では諏訪氏らとともに足利直義に属した。応永7年(1400年)の大塔合戦では井上左馬助光頼が高梨氏や須田氏、島津氏、小柳氏、布野氏、中俣氏などと共に大文字一揆衆の一翼として、守護小笠原長秀を破ったが、後に室町幕府から派遣された代官細川慈忠によって井上氏ら国人の反乱は鎮圧されている。
応仁2年(1468年)、隣接する須田郷に攻め入って逆に須田雅政によって討ち取られた記録がある。その翌年にも井上政家が隣接する高梨政高と狩田郷の領有を巡って争奪戦を展開している。そして室町時代後期には隣接する越後との関係を強め、越後守護家山内上杉氏と守護代長尾氏の争いに巻き込まれた。永正10年(1513年)高梨氏の支援を受けた長尾為景と対立する守護上杉定実を応援するため島津氏や栗田氏、海野氏らと越後に侵入しようとした。
戦国時代には北信濃に侵攻してきた甲斐の武田信玄に対して、井上清政(昌満)は越後の上杉謙信に属して対峙した。
信濃を占領した甲斐武田氏が織田氏の甲州征伐で滅亡した後、本能寺の変で織田政権も撤退した(天正壬午の乱)。この機に北信濃を支配下においた上杉景勝により、井上達満も帰住が叶ったが、上杉氏が豊臣政権下で会津へ転封されると井上氏も随行し、のちに米沢藩士となった。
この信濃の井上氏が嫡流であるが、播磨、安芸、三河などに同族と称する一族が存在する。また、時田氏(常田氏)、桑洞氏、保科氏、高梨氏、須田氏、佐久氏、関山氏、蘆田氏、赤井氏(丹波赤井氏)、荻野氏、内田氏などは系図上は井上氏の庶流である。
安芸井上氏
信濃井上氏と同族であり、南北朝時代、信濃守正頼の7代後裔の克光は後醍醐天皇に従って吉野に供奉し、克光の子の摂津守光純は山名氏満謀反の際に戦功を立てたことで備後国神石郡入江荘や安芸国高田郡山県荘の地1500貫を与えられ、安芸国へ下向して壬生高峯城を本拠とするようになった。以降井上氏一門は安芸において大いに繁栄した。
高田郡史によれば光純の子光教の妻は毛利豊元の妹であり、この時から井上氏と近隣の有力国人である毛利氏は親密になっていたとするが、井上・毛利両譜録にはその記述はない。
光教の孫で戦国時代の当主井上光兼が毛利氏に接近し、毛利弘元の信任を得て勢力を伸ばし、光兼の弟・井上元盛、光兼の子である井上元兼と井上元貞、光兼の弟・光貞の子である井上就在、一族の井上元吉の5名は、毛利幸松丸死後に毛利氏の家督相続を毛利元就に依頼する毛利氏宿老15名の連署状に署名し、元就の家督相続に貢献している。当時井上氏が毛利家中でいかに有力な譜代の家臣であったかが分かる。
このように安芸井上氏は大きな権力をもっていたので、主家毛利家に対する下剋上的な振る舞いが目立つようになり、毛利元就に警戒されるようになり、天文19年(1550年)7月12日から7月13日にかけての井上氏粛清により、元兼をはじめとして、井上就兼、井上就澄、井上元有など安芸井上氏の一族30余名が誅殺された。
しかし、この時別の理由や縁故などによって誅殺を免れた一族もあり、引き続き毛利氏に仕えた井上就在、井上元光、井上光俊、井上就正、井上就重や、小早川隆景に仕えた井上春忠などが知られる。これらによって安芸井上氏の血脈は保たれた。このうち井上就在の子孫が、明治の元勲である井上馨である。江戸時代の長州藩時代には大組518石の家をはじめとして多数の井上家が藩内に存在した。たとえば毛利斉煕の側用人の一人に「井上三郎兵衛」、文政年間の長府藩の城使に「井上丹下」の名がみえる。
明治に閣僚職を歴任した井上馨は明治17年(1884年)7月7日に維新の功により華族の伯爵に叙され、さらに明治40年(1907年)9月21日に日露戦争の功により侯爵に陞爵した。2代侯爵井上勝之助は外交官として駐ベルギー公使、駐ドイツ大使、駐イギリス大使などを歴任し、後に宮内省の宗秩寮総裁にも就任。3代侯爵井上三郎は陸軍少将まで昇進した陸軍軍人だった。
昭和前期に井上侯爵家の邸宅は東京市麻布区宮村町にあった。
三河井上氏
徳川氏に仕え江戸時代に大名になった三河井上氏も信濃井上氏の後裔と称しているが、同家の実際の出自は不明である。同家で実在が確実なもっとも古い人物は遠江国横須賀城の大須賀康高に仕えた井上清宗である。
その孫井上正就は1589年から徳川秀忠に150石で仕えるようになり、江戸幕府成立後の1615年に1万石の大名に取り立てられた。1622年には老中に出世して横須賀藩主5万2000石に加増されたが、旗本の豊島信満の殿中刃傷で死亡した。その後井上家は各地を転封させられ、丹波亀山藩に在封していた井上正岑の代の1718年の加増で6万石になった。最後に在封していたのは遠江国浜松藩だった。支藩として正就の弟井上政重を祖とする下総国高岡藩(1万500石)と正岑の弟正長を祖とする常陸国下妻藩(1万石)の2藩が存在した。
最後の浜松藩主井上正直は、藩内に国学研究会や遠州報国隊などが生まれていたことで藩論を勤王に導き戊辰戦争では官軍に参加した。明治元年(1868年)に徳川家達の駿府藩が維新立藩されるに伴い、上総国鶴舞藩に転封となり、翌年の版籍奉還で華族に列するとともに藩知事に転じ、明治4年(1871年)の廃藩置県まで務めた。
明治17年(1884年)の華族令により華族が五爵制になると正直の息子正英は、旧小藩知事として子爵に列せられた。支藩の藩主だった2家の井上家も同様に子爵家に列せられている。
昭和前期に鶴舞井上子爵家の邸宅は東京市世田谷区下馬町、高岡井上子爵家の邸宅は東京市世田谷区羽根木町、下妻井上子爵家の邸宅は名古屋市東区杉村町にあった。
系図
安芸井上氏
三河井上氏
- 1=浜松藩主家歴代、①=高岡藩主家歴代、ⅰ=下妻藩主家歴代。
藤姓井上氏(美濃井上氏)
美濃斎藤氏流長井氏族の井上氏。長井道利の三兄弟に始まり、主家の斎藤氏滅亡後、井上姓に改め、織田信長、豊臣秀吉に仕えた。織豊政権下で井上時利は760石を知行する旗本となったが、関ヶ原の戦いで西軍側に付いたため改易された。その後、子の井上利仲は罪を許され、江戸幕府の旗本として存続した。
東漢姓井上氏
阿知使主の後裔である東漢氏族の一つ。姓は忌寸。河内国志紀郡井於郷(大阪府藤井寺市道明寺付近)を本拠地としたとみられる。中華人民共和国陝西省西安市で墓誌が発見された奈良時代の日本人井真成をこの氏族の出身とする説がある。
脚注
注釈
出典
参考文献
- 浅見雅男『華族誕生 名誉と体面の明治』リブロポート、1994年(平成6年)。
- 新田完三『内閣文庫蔵諸侯年表』東京堂出版、1984年(昭和59年)。
- 小田部雄次『華族 近代日本貴族の虚像と実像』中央公論新社〈中公新書1836〉、2006年(平成18年)。ISBN 978-4121018366。
- 華族大鑑刊行会『華族大鑑』日本図書センター〈日本人物誌叢書7〉、1990年(平成2年)。ISBN 978-4820540342。
- 森岡浩『日本名門・名家大辞典』東京堂出版、2012年(平成24年)。ISBN 978-4490108217。
- 岡部忠夫『萩藩諸家系譜』琵琶書房、1983年(昭和58年)。ASIN B000J785PQ。
外部リンク
- 信濃井上氏 (日本語)
- 安芸井上氏 (日本語)
- 三河井上氏 (日本語)